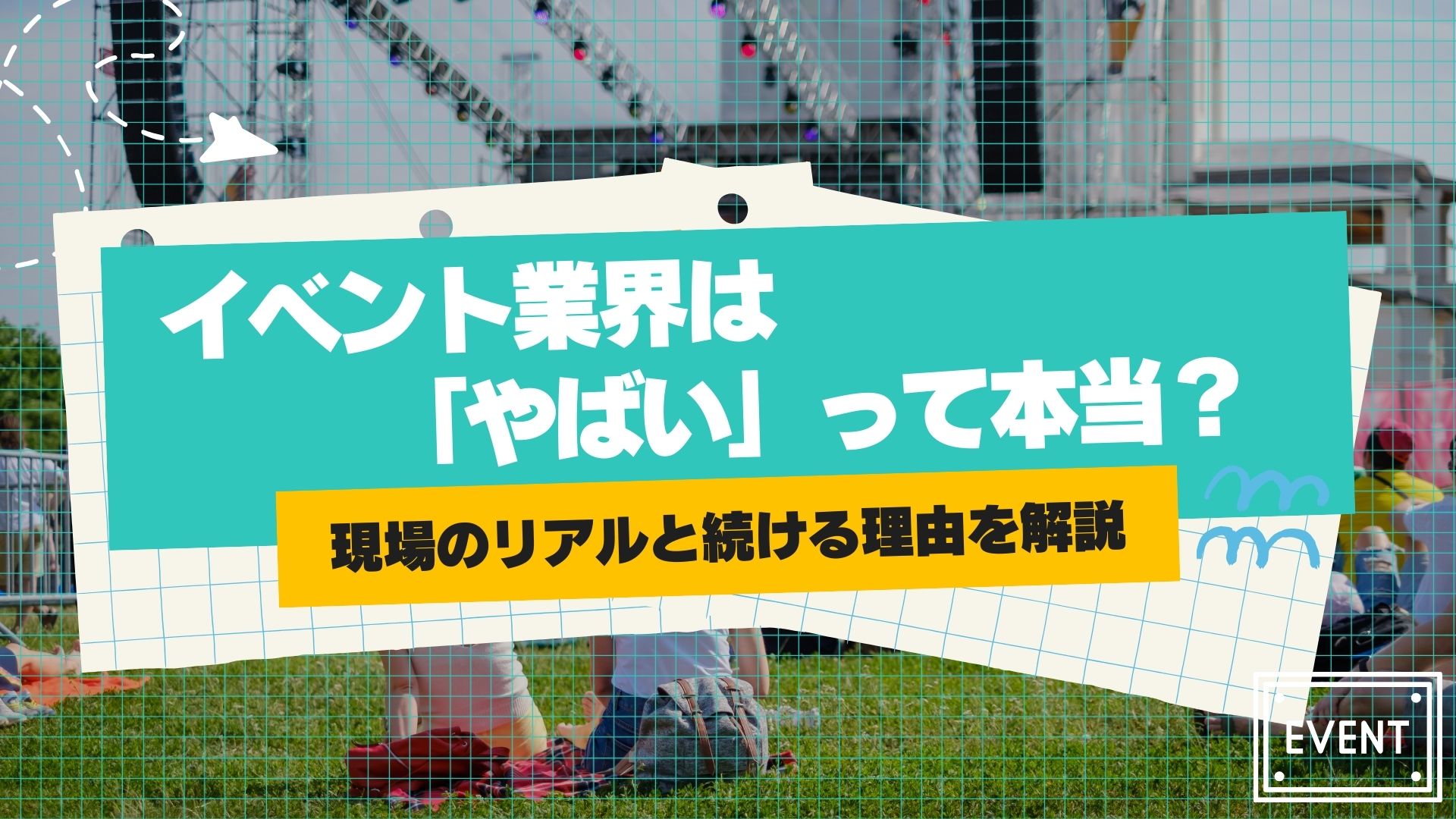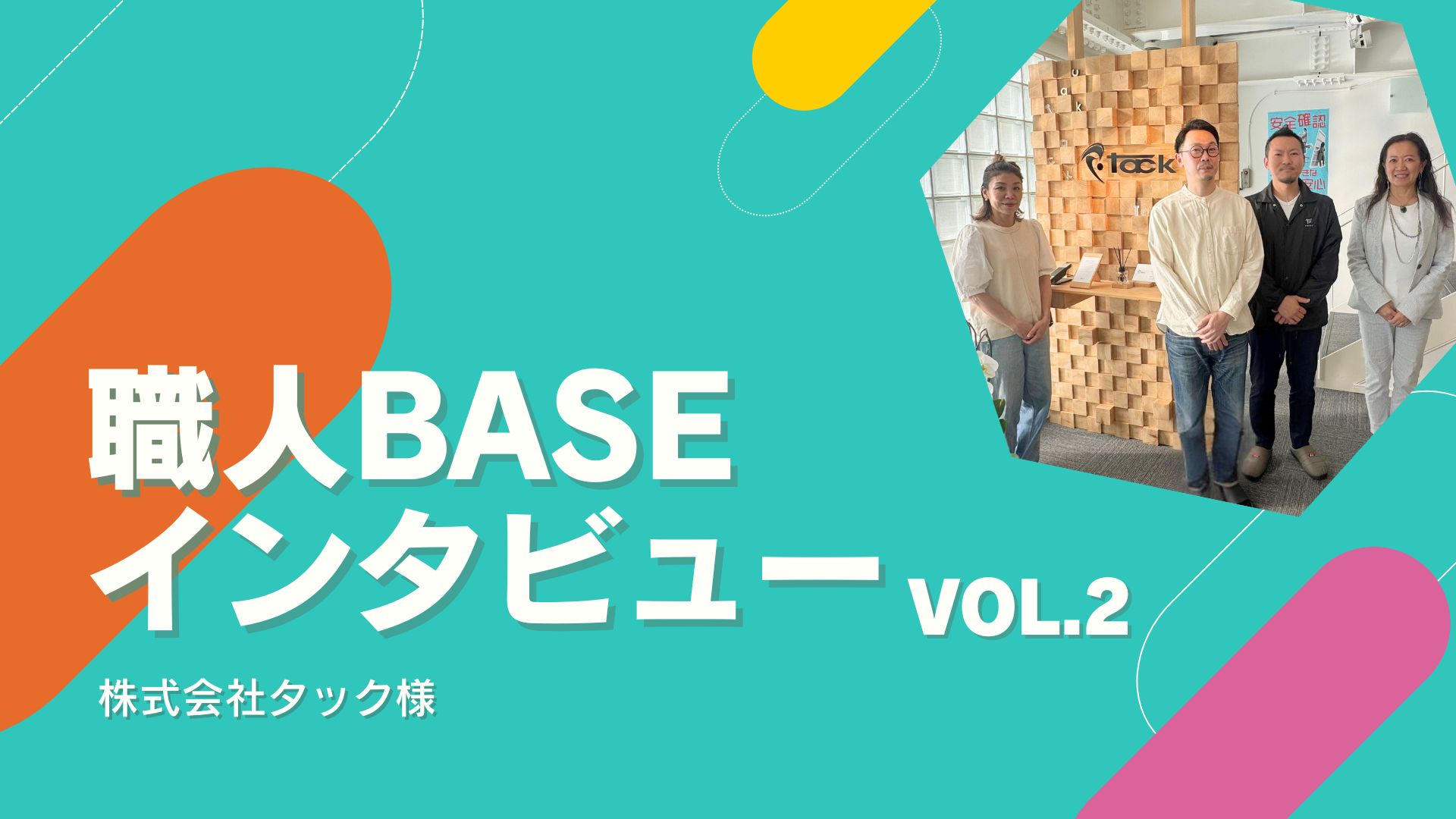「イベント業界ってブラックって聞くけど、本当に大丈夫?」
「長時間労働って当たり前?やりがいってあるの?」
そんなイメージや不安を持っている方も多いかもしれません。
確かに、イベントの現場にはハードな一面もあります。スケジュールはタイト、トラブルもつきもの、土日や連休も働くことが多い──。でも、それ以上にこの仕事には、人の心を動かす感動や、仲間とともに空間をつくり上げる達成感があります。
本記事では、イベント業界で働く上での「やりがい」と「課題」のリアルを整理しながら、この業界で長く活躍するために必要な経験・スキル・資格、そして未来のキャリアの描き方まで、現場視点で掘り下げていきます。
「この仕事が好きだ」と胸を張れるように、
今あらためて、イベント業界の魅力と可能性を見直してみませんか?
目次
イベント業界のやりがいとは?

イベント業界で働く最大の魅力は、自分の手で「人の心を動かす瞬間」をつくり出せることにあります。長い準備期間を経て迎える本番。観客の熱気、ステージの盛り上がり、クライアントからの感謝の言葉――そのすべてが、この仕事ならではのやりがいです。
特に、リアルな現場で参加者の笑顔や感動の声を直接受け取れるのは、イベント業界の大きな特権。「この空間をつくって本当によかった」と実感できる瞬間が、現場にはたくさんあります。
また、イベントの仕事は自分のアイデアや創造力をカタチにできるフィールドでもあります。演出プラン、空間設計、体験設計、参加導線まで。ゼロから企画を立ち上げ、チームと協力して実現していく過程は、まさに「現場発のクリエイティブ」。自分の考えた演出が観客の反応につながる喜びは、何度経験しても飽きることがありません。
加えて、イベントは多様な専門職が連携して一つの空間をつくる仕事。照明、音響、映像、施工、ディレクター、プランナー……。職域を越えて連携し合い、一つの目標に向かって突き進む一体感は、イベント現場ならではの醍醐味です。
さらに、案件ごとに関わる業界やテーマが異なるため、常に新しい知識や価値観と出会える環境に身を置けるのも魅力の一つ。初めて訪れる会場、未知のジャンル、クライアントのニーズに応える過程で、自然と自分の視野や対応力が広がっていきます。
*参考 就活市場
イベント業界の課題とキツサの正体

華やかなイメージの裏で、イベント業界が抱える現実的な課題も多く存在します。
ここでは、業界経験者なら誰もが一度は感じたことがある「きつさ」の正体を整理します。
平日・土日祝日の概念がなくなる勤務体制
イベント業界では、土日祝日や大型連休が“繁忙期”になることも多く、カレンダー通りの働き方が難しいのが現実です。
現場入りから設営、本番、撤収までを担当する場合は、早朝から深夜までフル稼働というケースも。
特に大型展示会や屋外イベントなどでは、深夜設営や徹夜作業になることもあり、体力的なハードさが避けられません。
長時間労働と年収のバランス
イベントの仕事は拘束時間が長くなりがちですが、給与水準がそれに見合っていないという声も聞かれます。
実際、イベント業界の平均年収は日本全体の平均よりも低い水準にあるとされており、特に若手のうちはアシスタント業務が中心になるため、報酬面に課題を感じる人も少なくありません。一方で、スキルを磨き実績を積むことで、大手案件の担当や若手の教育担当として、年収600万円以上を目指すキャリアパスも現実的です。
クライアントと現場の板挟み
イベントの現場では、クライアントの要望と実際の現場事情との間にギャップが生じることも珍しくありません。
「理想と現実のすり合わせ」は現場スタッフに委ねられることが多く、コミュニケーション力や調整力が問われる場面も多々あります。
技術職との連携や、当日の突発的な変更対応なども求められ、精神的なタフさが必要です。
人手不足と業務の属人化
慢性的な人手不足も業界全体の大きな課題です。特に設営・撤収といった体力仕事では、若手人材の確保が年々難しくなっており、一部のベテランに業務が偏る属人化も深刻です。
ノウハウが継承されにくく、急な欠員で現場が回らなくなるケースも見受けられます。
様々な外部要因にも左右されやすい
・気象条件(雨・風・猛暑)に影響を受ける屋外イベント
・コンペ主流による無償提案の慣習
・コスト削減のプレッシャーによる価格競争の激化
・サステナビリティやチケット転売などの社会課題への対応
など、現場以外の要素にも目を向ける必要があるのが、イベント業界の難しさでもあります。
*参考 Event Biz
それでも続けたい理由
多くの課題や「きつさ」があるにも関わらず、なぜイベント業界の仕事に情熱を注ぎ続ける人がいるのでしょうか。
人の感情を動かし、感動を生み出せる喜び
自分が関わったイベントで、目の前の観客が笑ったり涙を流したりする——そんな瞬間に立ち会えるのがイベントの仕事です。「誰かを楽しませたい」「感動を届けたい」という純粋な気持ちが、厳しい現場を乗り越える原動力になっています。
また、イベントはその場限りの「トキ消費」を演出する仕事でもあります。その一瞬のために積み重ねた努力が、参加者の記憶に残る体験として結実する。その特別な瞬間に携われる喜びは、何ものにも代えがたい報酬です。
自分のアイデアが社会を動かす
「こんな空間をつくりたい」「この体験を届けたい」という構想が、実際の空間や演出として目に見える形で実現する。イベントは、自己表現であると同時に、社会に新しい価値を届ける手段でもあります。
SDGsや地域共創をテーマにしたイベントでは、環境負荷の低減や地域の活性化といった社会的意義の高い成果に直接貢献できるのも特徴です。特に行政や大手企業との連携イベントでは、自分の仕事が地域や社会の課題解決の一端を担っているという誇りを持って働くことができます。
チームで達成する一体感と絆
イベントは、企画・制作・運営・設営など、多くの人が関わって成立するチームプロジェクトです。困難を乗り越えて成功したときに得られる達成感と仲間との絆は、言葉では言い尽くせません。
短期間で濃密な関係性が築かれやすく、共に走り抜いた仲間との信頼関係は、その後のキャリアにも繋がる財産となります。中には、何年にもわたって一緒にプロジェクトを回すパートナーシップが生まれることもあります。
変化し続ける刺激的な現場
AI、AR/VR、メタバース、ライブ配信、サステナブルイベント……イベント業界は常に進化を続けており、時代の最先端を肌で感じられる刺激があります。
特に最近では、デジタル技術とリアルの融合によるハイブリッドイベントが当たり前になりつつあり、テクノロジーに関心のある人にとっては、アイデアを実現できるチャンスが広がっています。自ら最新の知識をキャッチアップしながら成長できる環境は、知的好奇心の高い人にとって大きな魅力です。
自分自身も成長できる
イベント業界は「人間力」が磨かれる場でもあります。調整力、トラブル対応力、判断力、そして最後までやり抜く責任感——どれも一朝一夕では身につかない力ですが、この仕事を通じて確実に成長していくことができます。
また、若いうちからプロジェクトを任される機会も多く、自分の裁量で進められる範囲が広がっていく実感があります。クライアントとの交渉、スタッフのマネジメント、タイムラインや予算の管理など、ビジネスパーソンとしてのスキルアップも図れる環境です。
少しずつ変わる業界の働き方
業界全体としても、働き方改革やハラスメント防止など、少しずつ改善の動きが見られます。直接受注の強化、ビジネスイベントへの特化、フリーランスや副業の受け入れ体制の整備など、持続可能なキャリアを描ける環境づくりも進行中です。
残業時間の削減、年間休日の増加、ワークライフバランスの見直しなど、会社ごとに具体的な改善策を打ち出している例もあり、「業界=ブラック」というイメージは徐々に過去のものになりつつあります。
このように、課題の多い業界でありながらも、「人に感動を届けたい」「自分の力で空間を創りたい」「チームで何かを成し遂げたい」——そんな想いを持った人々が、今日も現場に立ち続けています。
イベント業界で働く魅力は、単なるやりがいだけでなく、「社会を動かす影響力」や「人としての成長」、そして「チームで何かを創る喜び」に満ちています。こうした魅力を理解し、共感できる人にとっては、これ以上に充実感を得られる仕事はないかもしれません。
イベント業界で重宝される資格・スキルとは

イベント業界では、資格よりも実践で培ったスキルや現場力が重視される傾向があります。ただし、業務の幅が広いからこそ、さまざまな知識や能力が必要になるのも事実。ここでは、業界で評価されやすいスキル・資格を紹介します。
現場で本当に求められるスキルとは?
■ 発想力と行動力
ゼロからイベントをつくるには、独自の視点と実行力が必要です。「こんな空間を演出したい」「この順番で参加者を動かそう」など、企画段階での柔軟な発想と、形にするための行動力は企画・制作職に欠かせません。
■ 論理的思考力
企画の意図を明確に説明できる力も必須です。
「なぜこの内容にしたのか」「この導線が最適な理由は何か」といった、裏付けのある設計がクライアントやチームの信頼につながります。
■ 進行管理・マネジメント力
スケジュール、予算、人員、リスク――あらゆる要素を把握しながら現場を回す管理能力は、プロデューサーやディレクター職で特に重宝されます。複数案件を同時進行する力も問われます。
■ コミュニケーション・プレゼン力
社内外の関係者と円滑にやり取りするための調整力、プレゼンで企画の魅力を伝える力は、どんな職種でも武器になります。現場では「伝え方ひとつ」で物事がスムーズに進むかどうかが決まることも。
■ 責任感と柔軟性
突発的な変更やトラブルはつきもの。冷静に対処するためには、責任感ある対応力と瞬時の判断力が求められます。代替案(プランB・C)をあらかじめ用意しておく慎重さもプロの証です。
■ デジタルスキル(企画 × テクノロジー × 現場力)
イベント管理システム、SNS運用、ライブ配信ツール、AR/VR演出、データ分析…
2025年以降のイベント業界では「デジタルの理解力」は必要不可欠です。現場目線とテクノロジーの融合が、今後の価値になります。
持っていると有利な資格
イベント業界に必須の国家資格はありませんが、以下のような資格はスキルの裏付けとして役立ちます。
| 資格名 | 内容とポイント |
| イベント業務管理士 | 日本イベント産業振興協会(JACE)認定。イベント制作の実務力と安全管理の知識を証明できる。特に官公庁や自治体案件で評価されることも多い。 |
| 建築士 | 会場設営や仮設構造物の安全設計など、建築的観点からイベント空間を支えることができる。特に空間デザインや設計業務と関わる場合に有利。 |
| 建築施工管理技士 | 大規模会場や仮設構造の設営時に必要な管理力を証明。設営現場での安全性・進行管理に関する信頼度が高い。 |
| 普通自動車免許 | 機材の搬入・運搬、郊外現場への移動など、日常的な業務で重宝される。必須条件としている企業も多い。 |
| CMP (Certified Meeting Professional) | 国際的なイベント・ミーティングの知識を証明する資格。海外案件や国際会議に関わる人向け。 |
| DES (Digital Event Strategist) | デジタルイベントに特化した国際資格。ライブ配信やバーチャルイベントに携わる人にとってはキャリアの強化材料に。 |
どれも「資格があるから採用される」というよりは、知識を体系化し、仕事の信頼度を高めるためのツールとして捉えると良いでしょう。
やっぱり現場経験がモノを言う
資格よりも評価されるのは、やはり実際の現場での経験と実績です。
- 学園祭や地域イベントでの企画・運営
- ライブハウスや劇場でのスタッフ経験
- アルバイトやボランティアでの裏方参加
など、小さな経験の積み重ねが次のチャンスにつながります。とくにフリーランスを目指すなら、「どんな現場で、どんな役割を担っていたか」が武器になります。
インターンや企業説明会への参加も、仕事の進め方や社風を知るうえで貴重な機会です。
*参考 イベントライフ!!
イベント業界の将来性とキャリアの考え方
イベント業界は、コロナ禍からの回復を経て、今まさに新たな成長フェーズを迎えています。特に2025年は、世界的な注目を集める「大阪・関西万博」の開催年。国内外からのイベント需要が高まり、業界全体が大きく活気づいているタイミングです。ここでは、そんな今だからこそ押さえておきたい、イベント業界の将来性とキャリアのあり方について紹介します。
万博開催で加速するイベント市場
2025年春に開幕した大阪・関西万博は、イベント業界にとってまさに追い風です。日本国内だけでなく、海外からの注目度も高く、リアルな“体験”を求める機運が再び高まっています。
コロナ禍で制限されていた大規模イベントも、各地で復活。音楽フェス、スポーツ、展示会、地域イベントなど、リアルとデジタルを融合させた「新しいイベントのカタチ」が次々と登場しています。
企業のマーケティング施策においても、SNSや動画広告に加えて「実際に体験してもらう場の提供」が重視されるようになり、イベントの役割はますます重要になっています。
テクノロジー融合で広がる可能性
業界の大きな変化のひとつが、デジタル×リアルの融合です。現地参加とオンライン参加を組み合わせた「ハイブリッドイベント」はすっかり定着し、参加者の幅が広がりました。
さらに最近では、AI・AR/VR・データ分析といった先端技術とイベント企画が一体となり、体験設計の自由度が大きく広がっています。
- AIによる参加者分析・コンテンツ最適化
- AR/VRを使った没入体験の提供
- 5Gによる高画質ライブ配信
- ブロックチェーンを活用したチケット管理やスポンサー連携 など
「最新技術を理解し、イベントに応用できる力」は、今後さらに重視されるでしょう。
多様化するキャリアと“イベント人材”の価値
従来の「イベント会社一択」という時代は終わり、キャリアパスも多様化しています。
- 企業のマーケティング部門でイベント担当として働く
- 自治体・NPOなど公共系イベントに関わる
- 特定分野(音楽・スポーツ・学会など)の専門職になる
フリーランスとして独立する - 演出や空間デザイン、テクニカル職への転向
いまや、イベント業界で培った経験はどこでも通用する武器。デジタルリテラシー、企画構成力、マネジメント力、現場対応力など、あらゆるビジネス領域で高く評価されています。
*参考 TIME.LY
求人選び・転職成功のために意識すべきこと

イベント業界は2025年も依然として「売り手市場」が続くと予想されており、特に即戦力となる中途採用のニーズは高まり続けています。
ただし、イベント業界は企業ごとに案件のジャンルや働き方、文化が大きく異なるため、「どこでもいい」という姿勢ではミスマッチが起きやすい業界でもあります。ここでは、転職を成功させるために意識しておきたいポイントを整理します。
案件ジャンル・業務範囲の確認
イベント業界とひと口に言っても、扱うジャンルは非常に多岐にわたります。企業のプロモーションイベント、行政や自治体主催の催事、スポーツ大会、音楽フェス、学会・カンファレンスなど、それぞれで求められるスキルや進行のスタイルも異なります。
また、企画・提案までを担うのか、進行・運営も含めて対応するのか、どこまでの工程に関われるかも企業によって差があります。自身の経験や希望キャリアに合ったフェーズ・ジャンルを選べるかどうかが、転職の満足度を大きく左右します。
チーム体制・社風の見極め
イベントはチームでつくるもの。だからこそ、「どんな人たちと働くか」は非常に重要です。
たとえば、少数精鋭で裁量大きく動ける環境を望む人もいれば、分業体制が整った大手で安定して働きたい人もいます。企業によっては、若手の抜擢が積極的だったり、現場社員との距離が近かったりと、風通しの良さや育成スタイルにも違いがあります。
応募前に社員インタビュー記事や公式SNSをチェックするのもおすすめ。可能であれば選考のなかで直接社員の雰囲気に触れる機会があると、よりイメージしやすくなります。
自分の経験が活かせるか
過去にどんな現場に関わってきたか、どんな役割を担ってきたか——これは中途採用において大きな評価ポイントです。
例えば、自治体案件での丁寧な運営経験、音楽イベントでの設営ディレクション、BtoB向けイベントでのマーケティング連動型企画など、自分の得意領域が、応募先の仕事とどう重なるかを冷静に見極めることが重要です。
一方で、少し違うジャンルやポジションへのチャレンジを考えている場合は、「どのスキルが応用できるか」「新たに伸ばしたい能力は何か」といった視点で、成長機会のある職場かどうかを見るのも大切です。
まとめ

イベント業界は、華やかな表舞台の裏側に、地道な努力と責任の重さを伴うリアルがあります。たしかに「きつい」「やばい」といった声があるのも事実ですが、それ以上に、多くの人に感動を届けるという大きなやりがいにあふれた仕事です。
今、業界はコロナ禍からの回復を経て、AIやAR/VRなどのデジタル技術と融合しながら新たな進化のステージに突入しています。2025年の万博開催をはじめ、リアルとオンラインが融合する「体験の再構築」が加速する中で、企画力や現場対応力だけでなく、テクノロジーの理解やデータ活用スキルも重要視されるようになりました。
この変化の時代に、必要とされているのは、「人を楽しませたい」という情熱と、状況に応じた柔軟な判断力、そして仲間と一緒に挑戦を楽しめるマインドです。経験を武器にキャリアを深めたい方にとって、今はまさに大きなチャンスのタイミングと言えるでしょう。
現場で培った経験や感性を、次のステップにどうつなげるか――。そのヒントを探しに、まずは自分に合った案件や働き方を知るところから始めてみませんか?
🔍 あなたに合った案件を探すなら
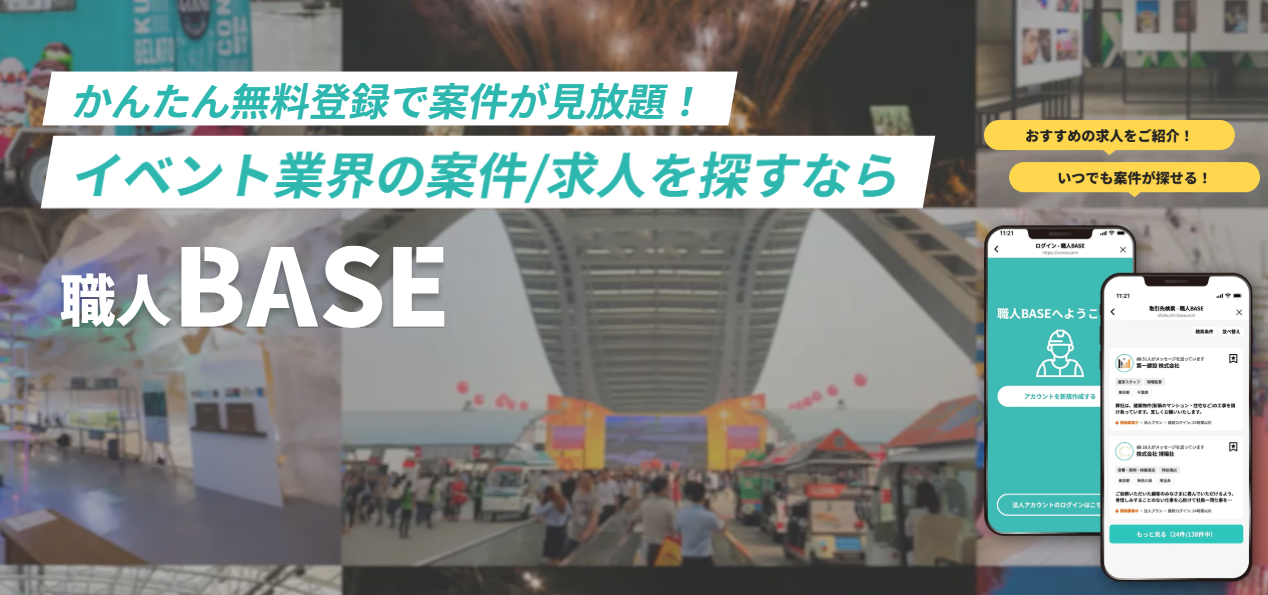
▶ イベント業界の求人・案件を探す(職人BASE)
※経験者向けの案件が中心です。気になる案件があれば、お気軽にご相談ください。